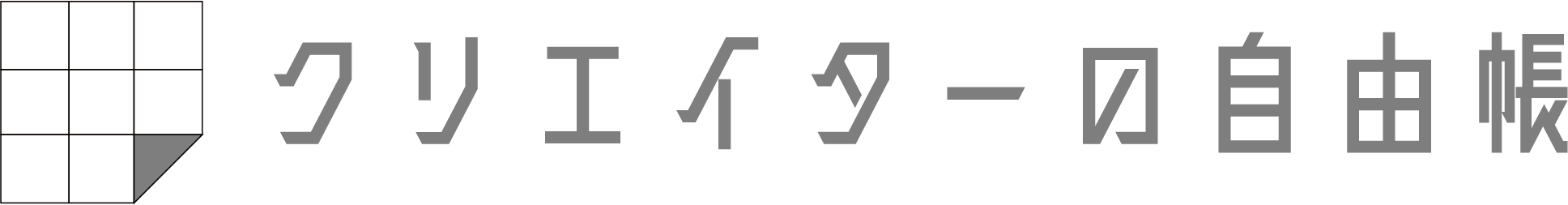D1K creative tips #4|社史/周年記念誌って?
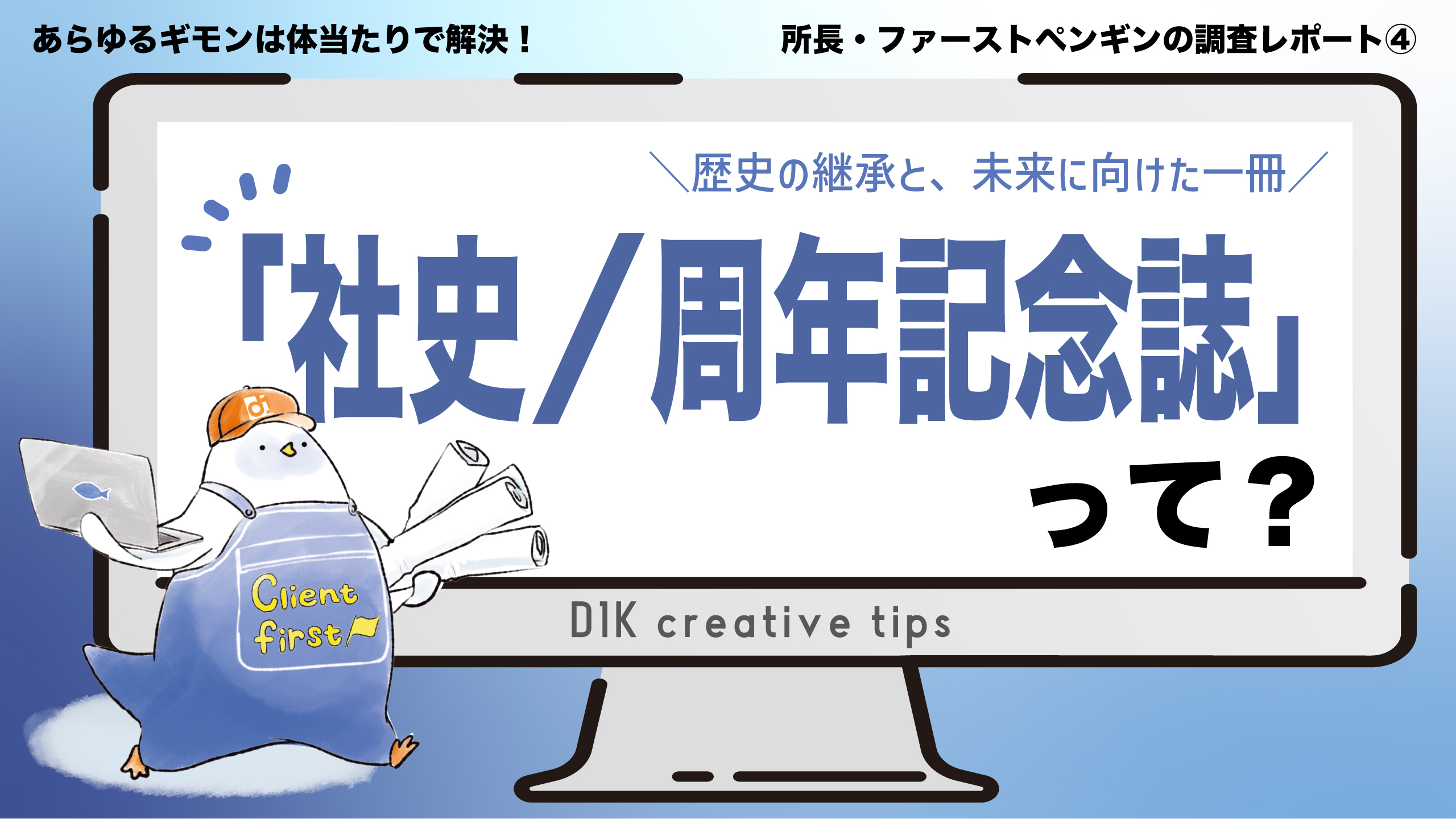
企業・行政・学校などが節目を迎えるにあたり、おすすめのツールが「社史/周年記念誌」です。これまでの歴史をふり返るだけでなく、未来にむけた方向性を共有するのに最適で、周年事業において欠かせない存在であると考えています。しかし、いざ記念誌を制作しようと考えても、前任者がいなく、初めて担当するケースがほとんどで、企画・編集面に不安を抱えてしまうことが多いと思います。
そこで記念誌制作における、ページ構成のポイントや編集のヒントをご紹介します。
記念誌の効果
これまでの歴史と未来へのメッセージを盛り込む記念誌で得られる効果は多岐に渡ります。
- [営業面]関係者への学校・企業の存在意義の発信
- 記念誌は、その他の広報物に比べて、歴史や功績を詳しく説明することができます。
- [教育面]社員へのインナーブランディング
- 学校・企業の歴史や理念を社員に共有することができます。また、編纂委員会の運営など、制作過程そのものが貴重な体験になると考えています。
- [採用面]採用活動でのPRツール
- 学生や求職者に対して、自社の魅力を訴求することができます。
- [保存面]文化や技術の変遷など、歴史の継承
- 上質な製本によって、これから先、何十年も会社の歴史を残していくこともできます。
また、最近では、印刷にこだわらず、「電子書籍化」や、使用した資料をデジタル化した「デジタルアーカイブ」にするケースも増えています。
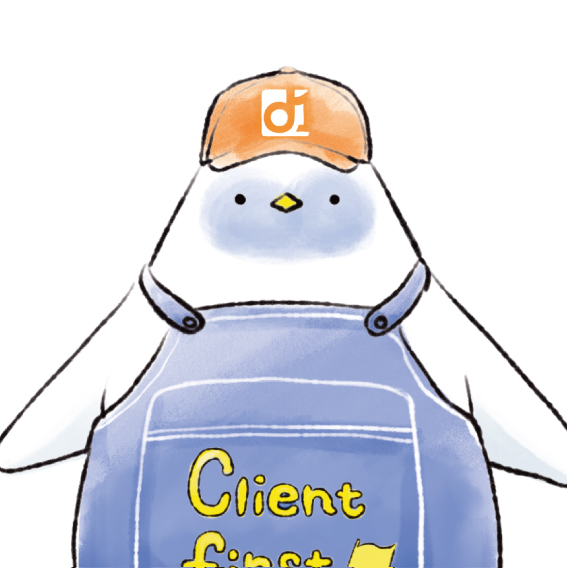
社内外に向けた、新しい価値を生み出すきっかけになります!
記念誌制作の進め方
チラシや広告などの宣伝活動と違い、「全て自作で」あるいは「全て外注で」が難しいのが記念誌制作になります。ページの構成から誌面の企画、過去の資料の整理、取材、原稿の制作、印刷、製本など、人数も経験も必要な作業となるため、「自社でなんとかする部分」と「外注に任せる部分」を分けながら、分担・協力体制を構築する必要があります。
そのために必要なのが「編纂委員会」です。簡単に言えば「記念誌制作チーム」をつくることです。
通常の広報宣伝の場合、外注に企業のイメージやプロモーションの目的を話せば、ビジュアルのアイデアから、広告にかかる素材(取材や撮影などを行い、写真や原稿などをつくる)の用意は外注がやってくれるので、ある程度「指示とチェック」「おまかせ」で完了できます。
しかし、記念誌の場合は、その「素材」となるものが、「過去のデータ、資料、写真、取引先からの寄稿文」など自社固有の情報に及ぶため、どうしても「自力でやっていただく」仕事量が結構大きくなってしまいます。
そのため、ご担当者以外にもメンバーを募って、外注スタッフと共にチームを作り、「一緒に記念誌をつくっていく」必要があるのです!
外注の制作会社としても、その素材の有無や量・質によって、「できる表現」「できない表現」を知る(提案できる方向性を決める)重要な要素になります。
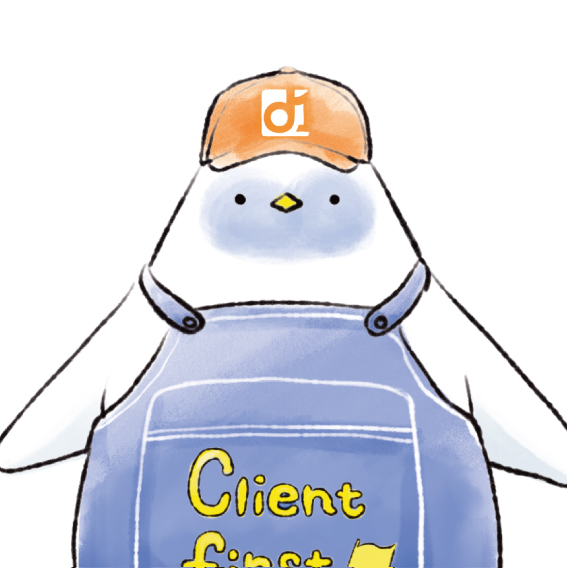
チームとして動くことが、スムーズな進行には欠かせません!
記念誌のタイプは自由!
記念誌には、大きく2つの型があります。
1つは、従来の「社史・年史」と呼ばれる、記録を残すことを目的としたタイプです。過去に起きた出来事や当時の状況を、文字と写真、年表などで残します。厚手・布張りの表紙や、ハードケースなど、比較的「書籍」「資料」「しっかりと後世に伝えていく」「重厚さ」といった印象が強いものになります。
もう1つ、最近のトレンドになってきているのが、読み物を意識した、自由なレイアウトのタイプです。雑誌のようなレイアウト、イラストや漫画を活用したテイスト、インタビューや座談会などの紙面内企画も多め、ページ数もさほど多くなく、小冊子や中綴じの装丁など、比較的「雑誌のよう」「読み物」「手に取りやすい」「手軽さ」といった印象が強いものになります。
どちらも、それぞれの良さがありますので、自分たちのスタイルをぜひ見つけてください。
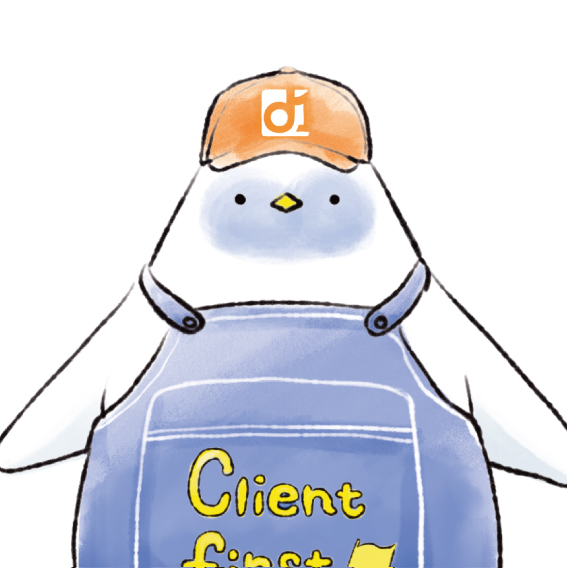
書籍にとらわれず、自由な発想で記念誌をつくりましょう!
記念誌には何を載せる?
オーソドックスな記念誌の場合、誌面に載せるコンテンツとしては、
- 代表者の挨拶
- 歩み(これまでの変遷)
- 特別企画(座談会やインタビュー)
- 関係者の寄稿文・コメント
- 資料(社内資料や年表)
となります。(もちろん、これ以外の企画を盛り込んでも構いません。)
このなかで、大きなカギとなる部分が「歩み」になります。 ページ数としても一番多い割合を占め、記念誌のイメージが反映されるコンテンツのため、これを表現する企画はとても重要になります。しかし、前述の通り、過去資料に頼る部分が大きいコンテンツでもあるため、素材の状態によって、どのような構成で誌面をつくっていけるかが大きく変化します。
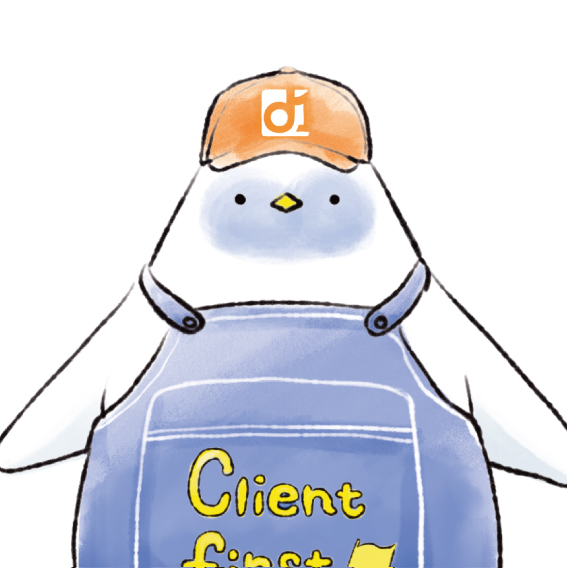
お客様が所有する素材によって、それぞれに合う企画を考える必要があります!
気になる制作期間や予算は?
これまでお伝えした通り、過去の資料の掘り起こしから、全体の企画を考え、関係者の日程を調整して、具体的に制作をして、原稿のチェックをして、印刷へ……と、各作業にかかる時間がチラシやポスターをつくる場合より多くかかるため、記念誌一冊を作り上げるには、およそ「1〜2年」をかけて制作するケースが多いです。
そのため、周年事業として発刊する場合は、1〜2年前には検討に入っていただく必要があります。
また、制作・印刷にかかる費用については、記念誌の仕様(全体の企画構成・ページ数・部数)によって変動するため一概には言えませんが、これまでのD1K-LABの実績に基づく調査としては、およそ「200〜300万円」になるケースが多いです。
もちろん、予算に合わせた周年事業ツールを仕様設計から検討することもできますので、まずは、制作会社にご相談いただくとよいと思います。
いかがでしょうか?
- 記念誌は、使う人の数だけ役割をもつ、ユーティリティツール
- 仕様設計によって、新しいコミュニケーションを生むことができる
- 編纂委員会でチームを作り、過去資料など「みんなで一緒につくる」ことが重要
- 動き出すなら1〜2年前
ということを覚えておいていただければ、より良い記念誌をつくることができると思います。
いずれにしても、詳しく確認して欲しいときは、専門の制作会社にご相談してみてください。